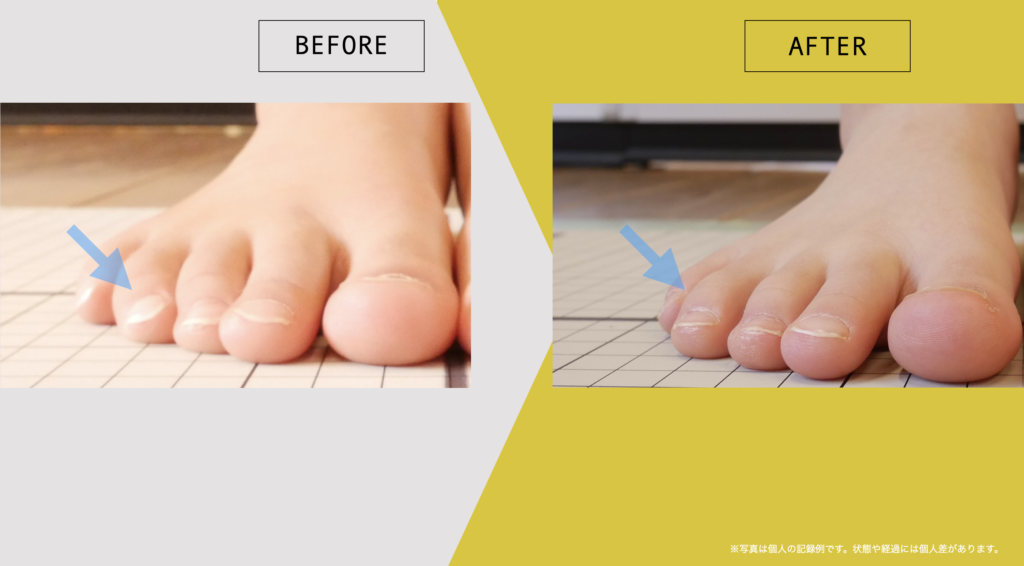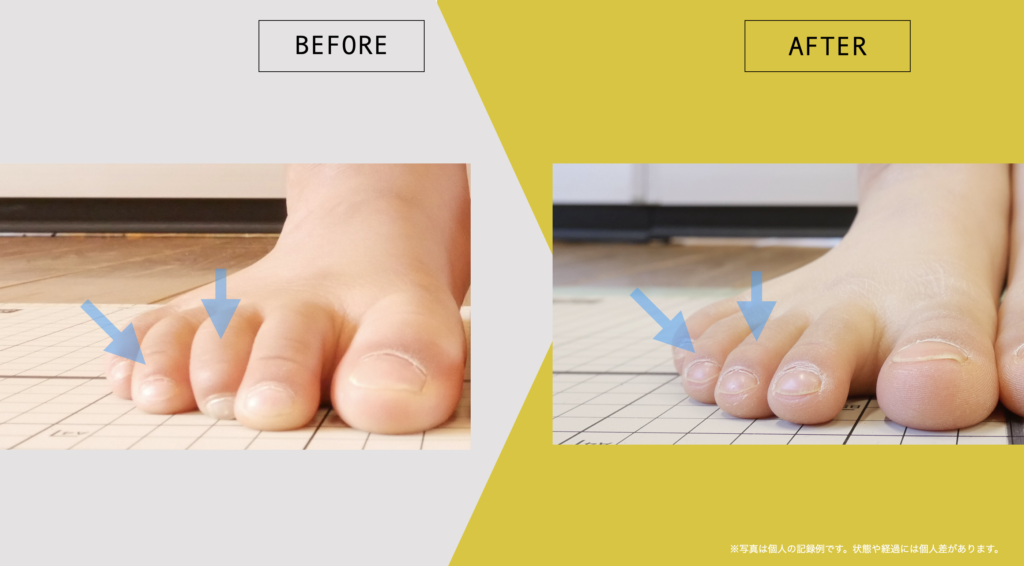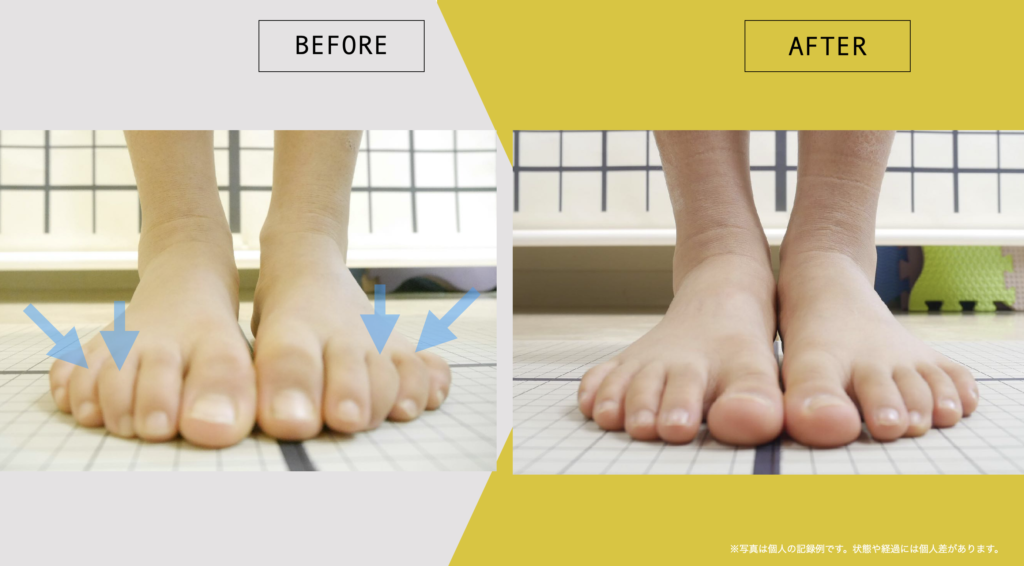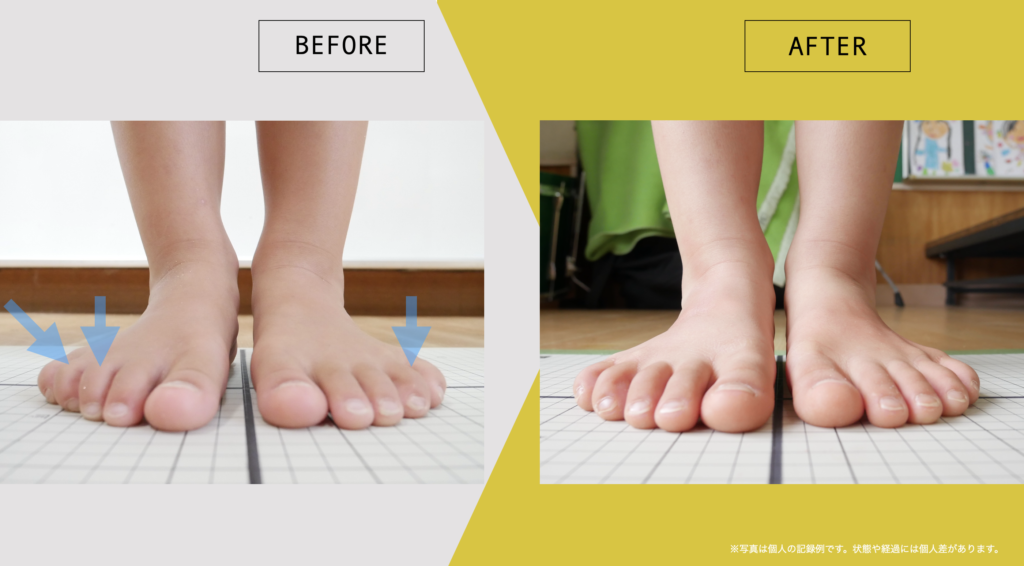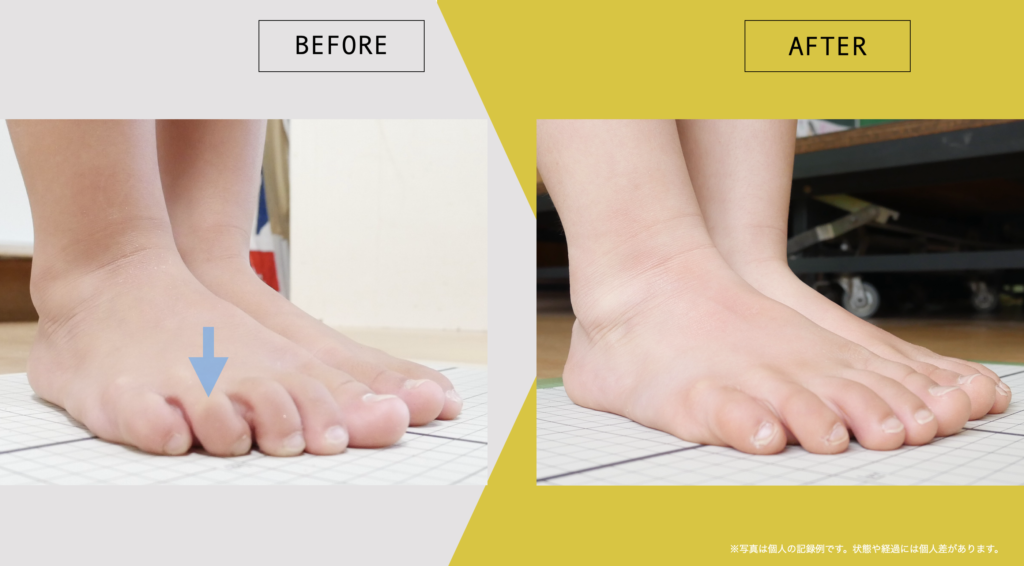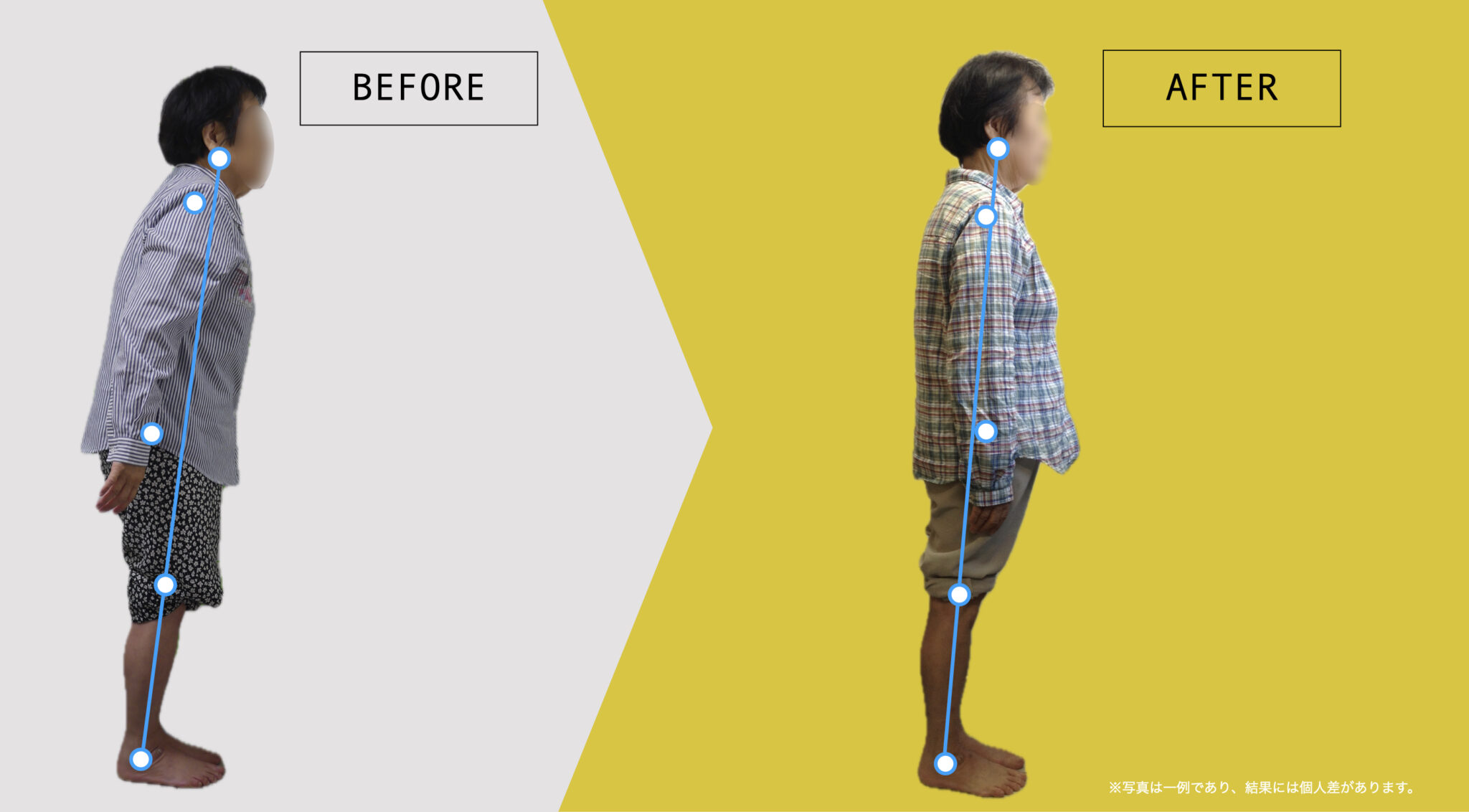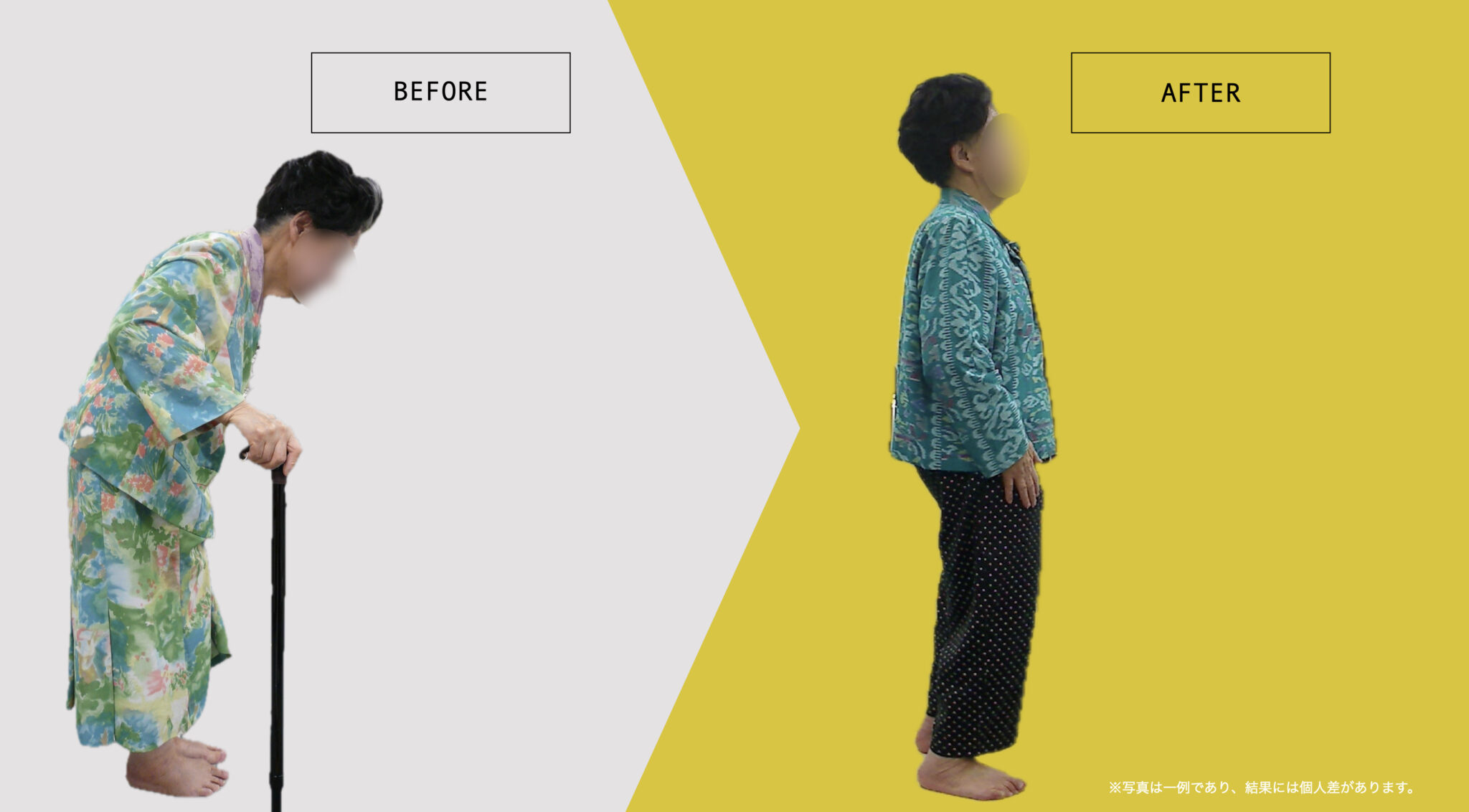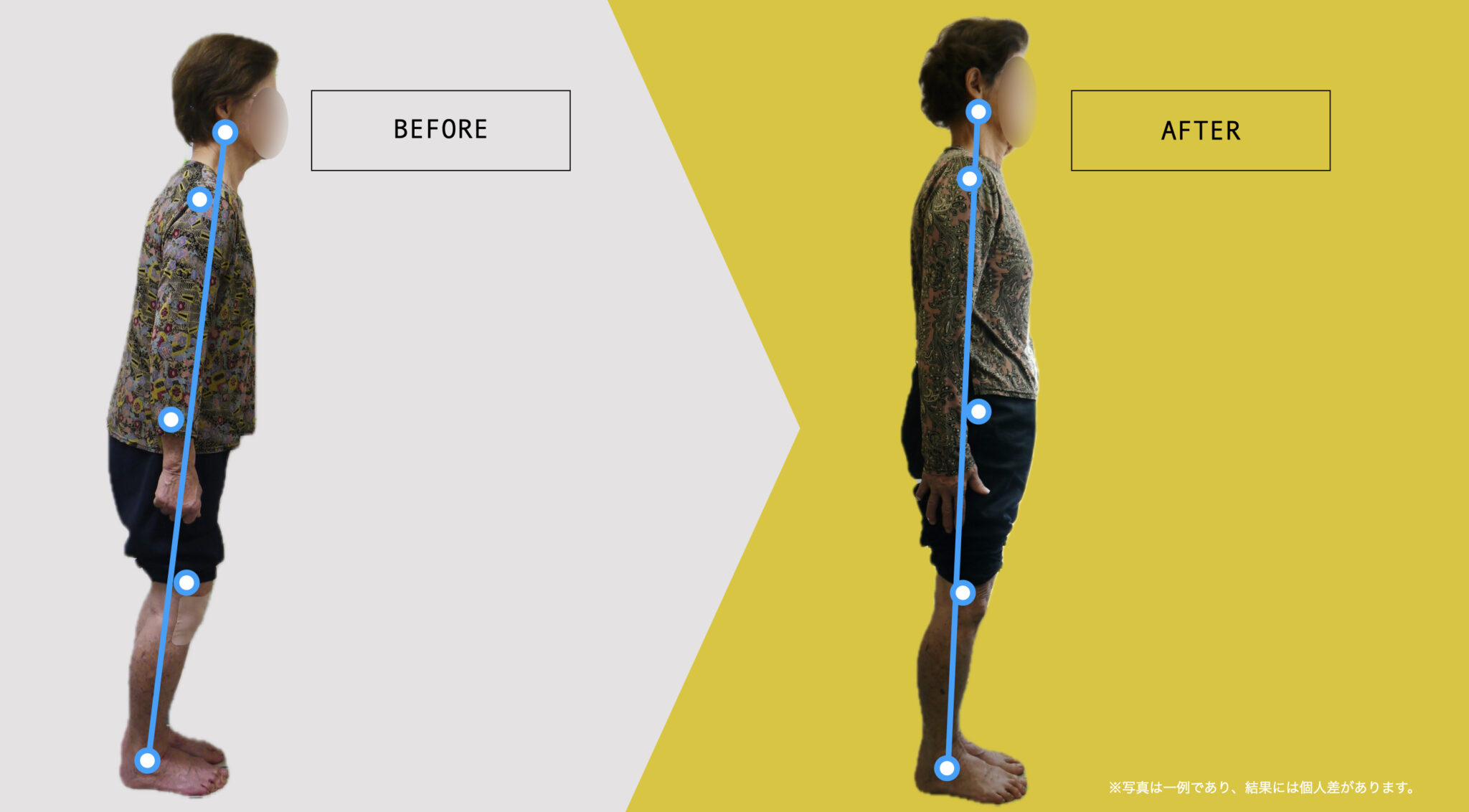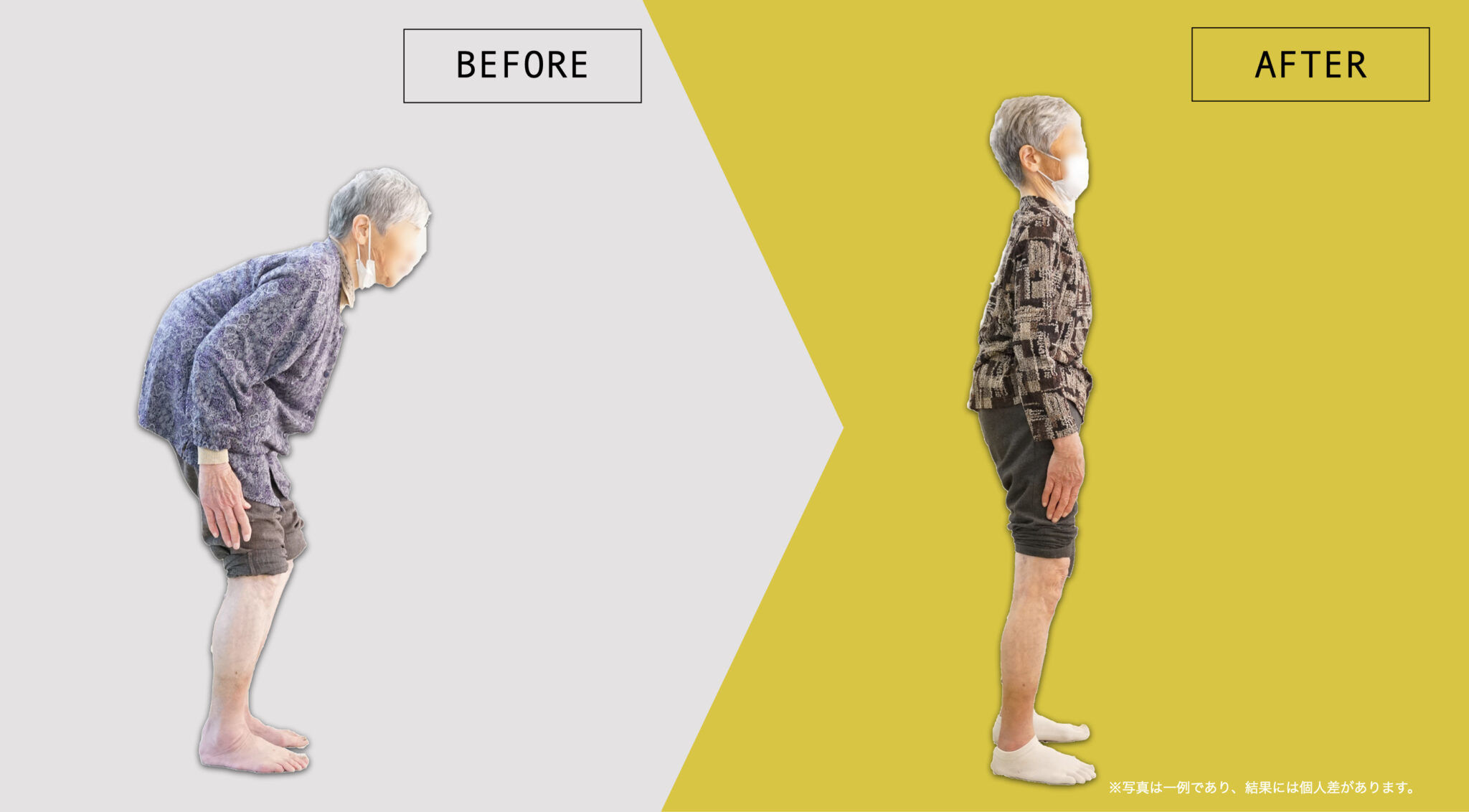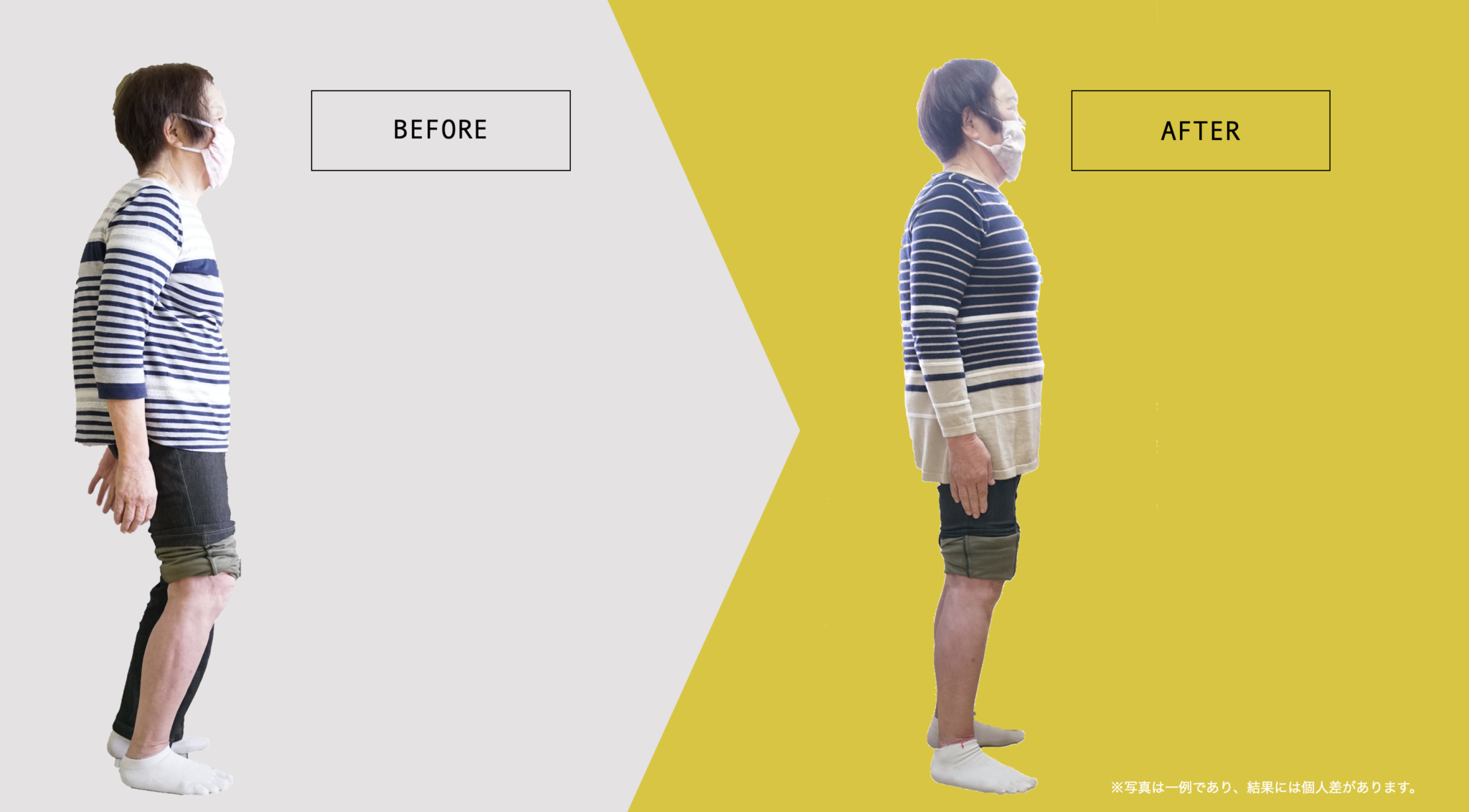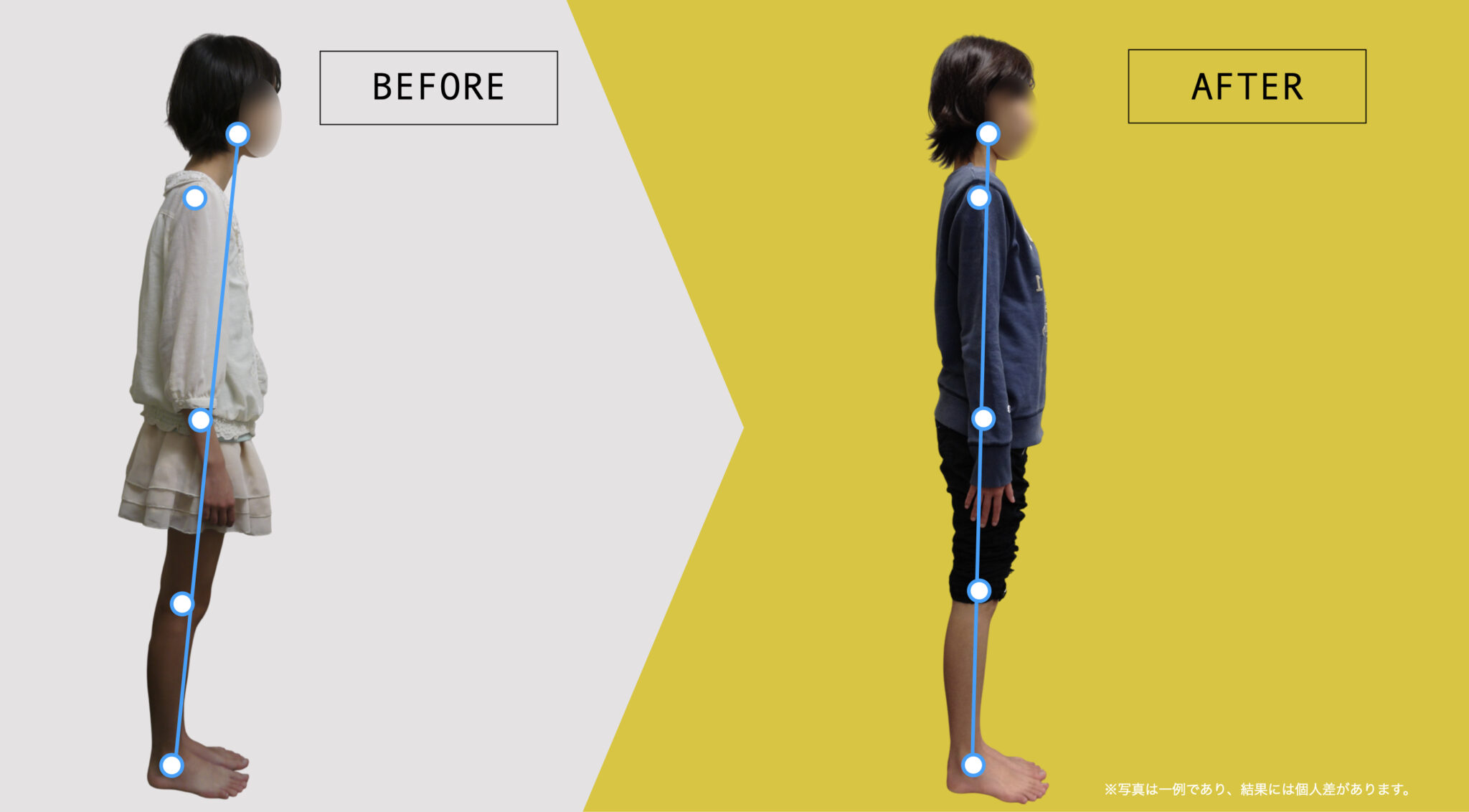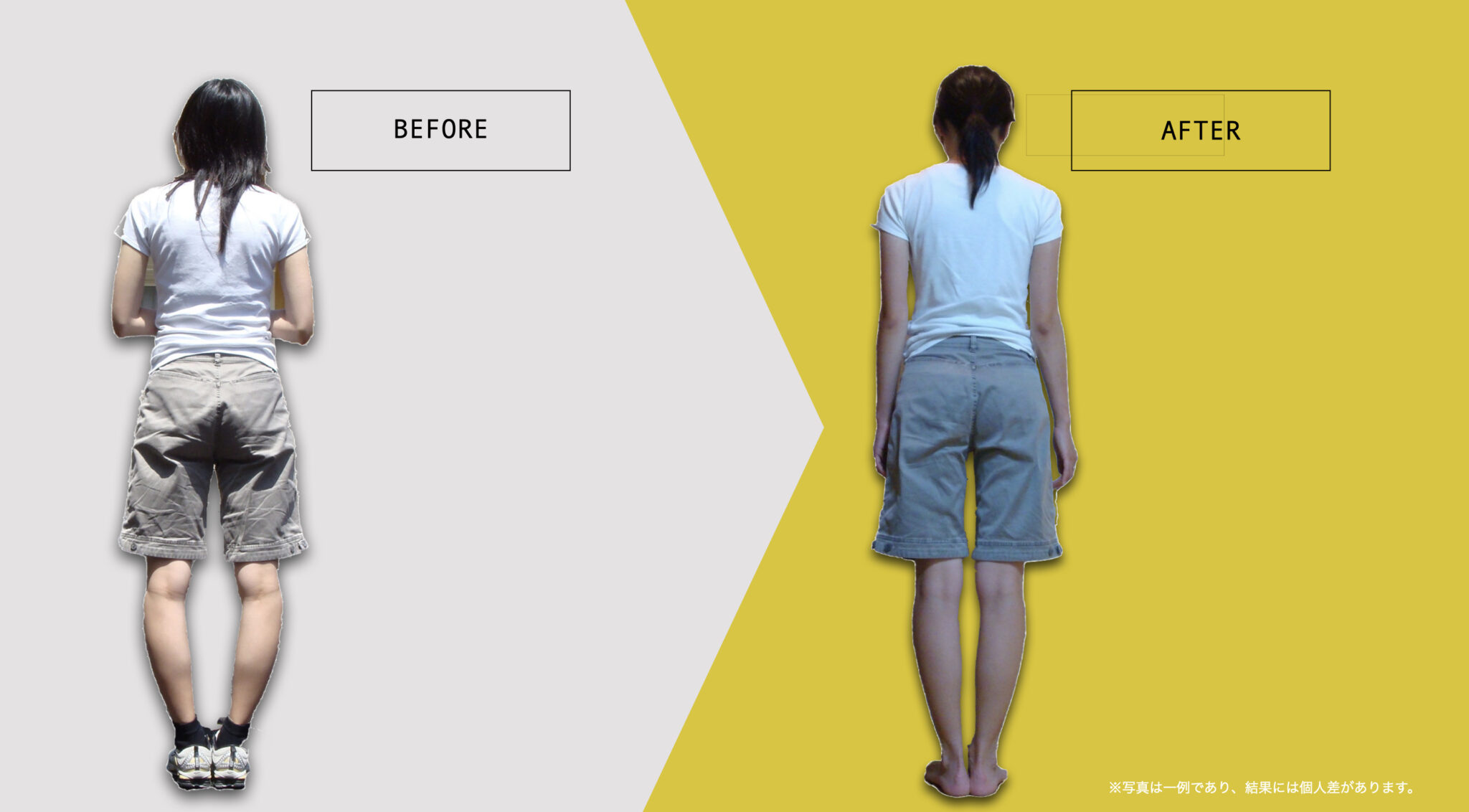【医療監修】外反母趾サポーターは本当に効果がある?「治った」「痛い」は本当か、専門家が整理します

はじめに|サポーターをつければ外反母趾は良くなる?
こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。
「親指のつけ根が痛い」
「靴が当たってつらい」
「サポーターで形が戻るのでは?」
外反母趾の悩みを抱える方の多くが、このような期待を持ってサポーターを購入します。
しかし私は、10万人以上の足を診てきた臨床経験上、
“固定=矯正” という発想には限界がある
と感じてきました。
本記事では、
- サポーターで何ができて
- 何ができないのか
- 外反母趾がなぜ「元に戻りやすい」のか
- 本質的なアプローチとは何か
を 解剖・臨床・神経制御の観点 から整理します。
外反母趾とは?──本当の原因は“足指の機能不全”にある
一般的には、
- ハイヒール
- 幅の合わない靴
- 遺伝
- 靭帯の緩さ
などが原因と言われています。
しかし、私の臨床データ・観察研究から見えてきたのは、
✔ 外反母趾は「足指の機能不全 → アーチ崩れ → 骨配列の変化」という順序で進む
という構造的パターンです。
■構造の流れ(とても重要)
1. 浮き指・屈み指になる
接地性が失われ、足指が働きにくい
2. 足底筋群が低下する
短母趾屈筋・母趾外転筋・長母趾屈筋・骨間筋などが機能低下
3. 開帳足になる
中足骨が横に広がり、アーチが支えられない
4. 母趾内転筋の張力バランスが崩れる
→ 親指が徐々に小指側へ引かれやすくなる
外反母趾は単なる“指の角度の問題”ではなく、
指が使えなくなる → 足全体の支えが失われる
という「機能の連鎖」で起こるのです。
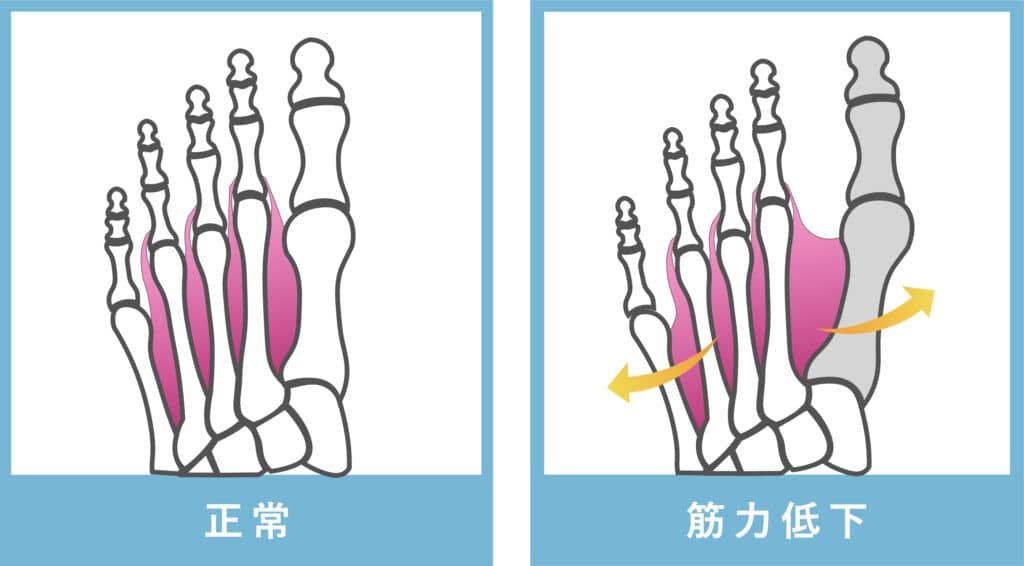
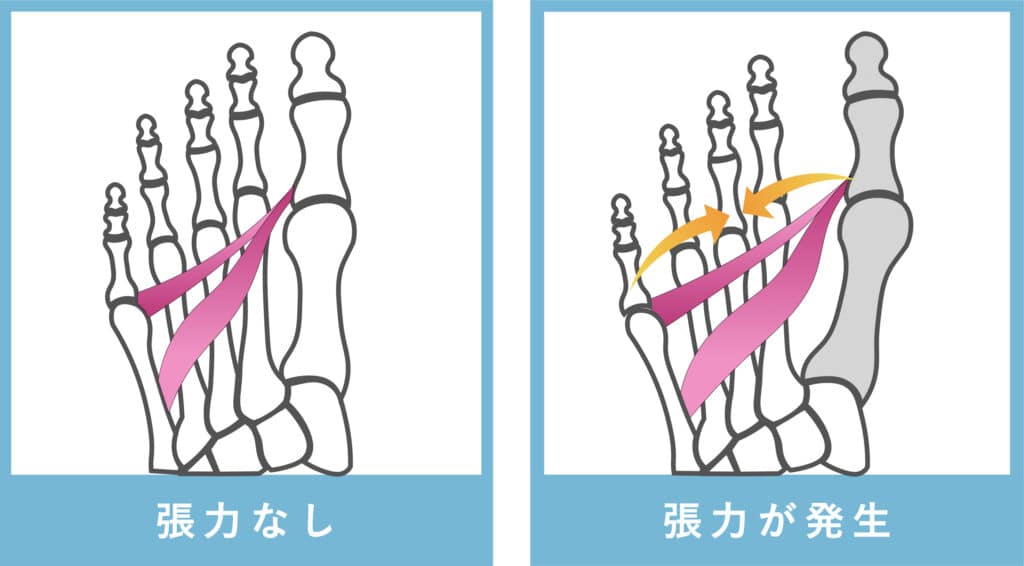
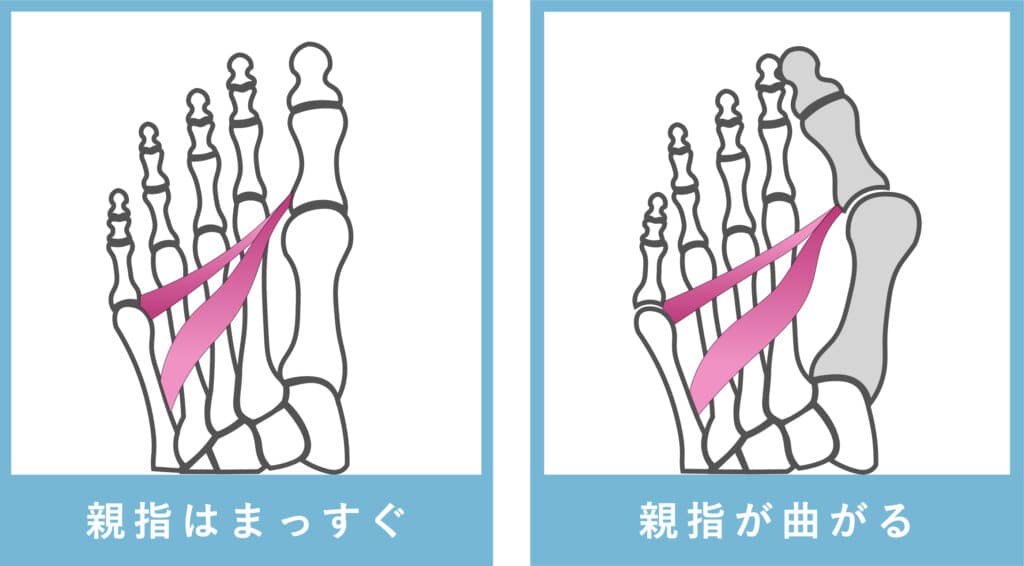
私はこの構造を「Hand-standing理論」と呼んでいます。
人の足は、単なる土台ではなく、
手の指と同じように“感じて・支えて・微調整する”ための器官です。
本来、姿勢や歩行は「足指の感覚と動き」によって制御されています。
手で逆立ちをしたとき、バランスを取るのは腕や体幹ではなく、
床を探る「指」です。
足も本来は同じで、指が接地し、動き、情報を脳へ返すことで
全身の安定が保たれています。
しかし外反母趾では、
足指が接地せず、動かず、感覚が遮断されやすくなる。
この状態で形だけを固定しても、
身体は“立ち方・使い方”を学び直すことができません。
これが、サポーターだけでは外反母趾が戻りやすい理由です。
では、サポーターに頼らずに
“本質的な対策”とは何なのか?
▶︎【医療監修】外反母趾は自分で治せる?手術を考える前に知っておきたい原因と自宅対策

外反母趾サポーターの種類と “できること・できないこと”
市場には4つのタイプがあります。
① テーピング型

👉 指を外側に引く“矯正”が目的
👉 違和感は少ないが 固定力は弱い
できること:着用中の補助的なアライメントサポート
難しいこと:筋機能・神経機能の再学習
② シリコンスペーサー型

👉 指の間に挟んでスペースを作るタイプ
できること:摩擦軽減・感覚の補助
難しいこと:骨配列・筋活動の変化を長期的に作る
③ 靴一体型サポート(外反母趾対応靴)
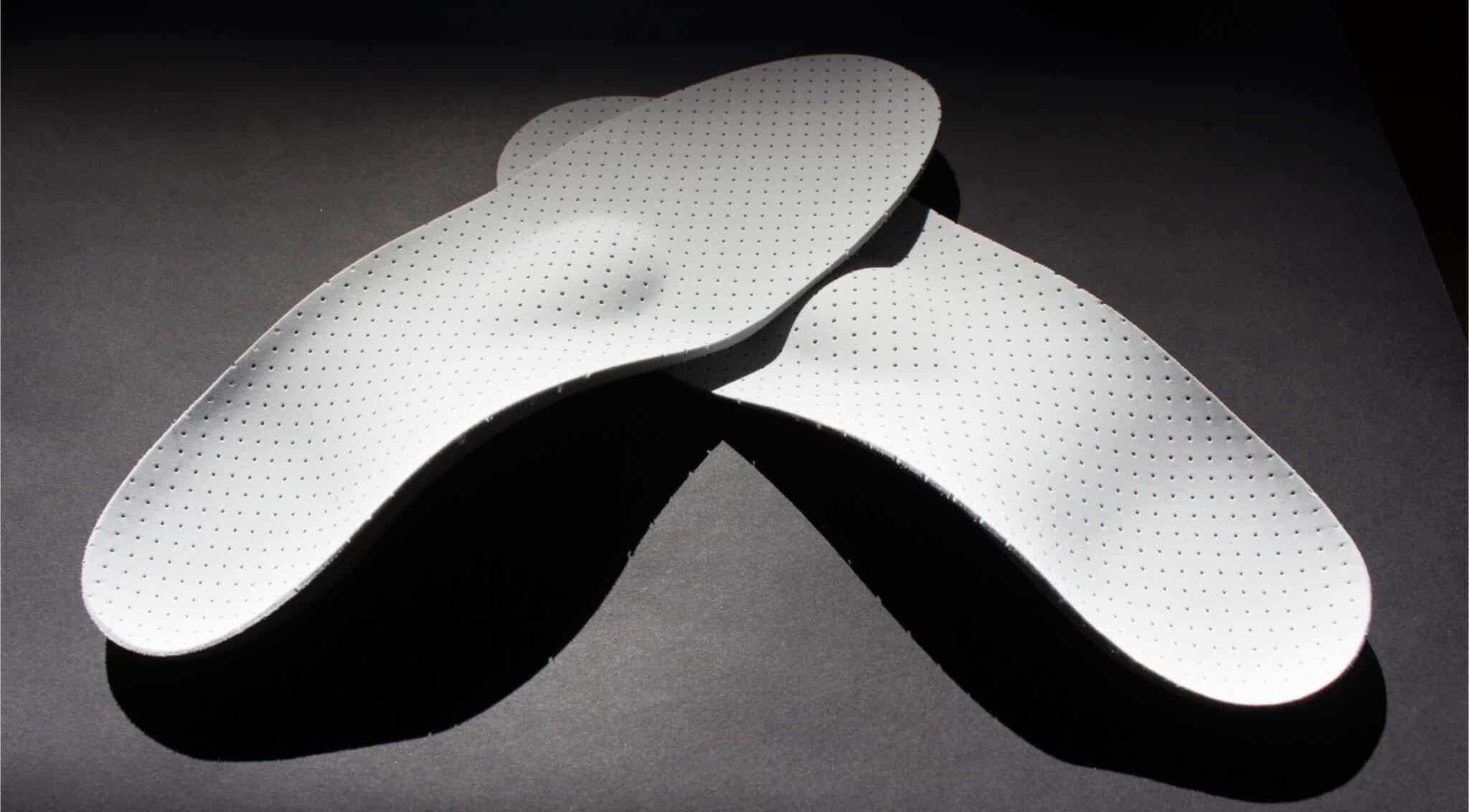
👉 履いている間の安定性は得られる
できること:歩行時の負荷軽減
難しいこと:脱いだ瞬間に元の状態へ戻る

④ 夜間固定ブレース

👉 プラスチックなどで角度を物理的に補正
できること:着用中の位置保持
難しいこと:外した後の再現性(筋機能が変わらないため戻りやすい)
サポーターの“限界”はどこにあるのか?
■限界①:筋肉と神経の働きを“止めてしまう”ことがある

固定が強すぎるサポーターは、
- 母趾外転筋
- 短母趾屈筋
- 足底骨間筋
など、外反母趾と強く関係する筋活動を抑制させます。
= 支えられている間だけは楽だが、外すと戻る
■限界②:変形の「角度」だけに注目してしまう

外反母趾は
角度の問題ではなく、機能の問題
です。
角度よりも重要なのは、
- 指が接地しているか
- 押し出せるか
- 開閉できるか
- 神経からの指令に反応できるか
という “動きの質”。
■限界③:サポーター依存で筋活動が低下するリスク
長時間の着用により、
本来使われるべき筋肉が活動しなくなる
ことがあります。
これは臨床で非常に多いケースです。
効果が出やすい人・出にくい人の特徴
✔ 効果が出やすい傾向がある人

- 軽度〜中等度の変形
- 足指の自動運動(曲げ伸ばし)が残存している
- 足底筋群がまだ働ける状態
✔ 効果が出にくい/悪化しやすい傾向がある人
- 中等度〜重度で関節形状が大きく崩れている
- 靭帯が短縮している
- サポーターに依存して筋活動が低下している
特に「固定しすぎ」は注意が必要です。
特に、痛みが出ている時期のサポーター使用は注意が必要です。
「固定すれば楽になる」
という判断が、
結果的に筋活動の低下や感覚遮断を招き、
痛みや変形を長引かせてしまうケース
も少なくありません。
痛みが出ている時にやってはいけない行動については、
以下の記事で整理しています。
▶︎ 外反母趾が痛い時にやってはいけないこと
.202-scaled.jpeg)
選び方・使い方|もっとも多い失敗
❌ よくある失敗
- きついサポーターで血流障害
- サイズ不一致
- 着用しすぎて感覚鈍麻
- 靴との相性が悪く擦れる
- サポーターだけで治ると思い込む
✔ 正しい選び方
- 足指が「動く余地」がある構造
- 痛み軽減か、動きの補助か、目的を明確に
- 使用時間は限定
- 靴と合わせたフィッティングを行う
外反母趾を支える“本質的アプローチ”
結論として、外反母趾の鍵は 「機能の再教育」 です。
■再教育のポイント
- 母趾外転筋・短母趾屈筋の再活性化
- 浮き指・屈み指の改善
- 足底アーチの再構築
- 正しい歩行パターンの習得
つまり…
✔ “形”を整えるだけでは不十分
✔ “動かせる足”を取り戻す必要がある
【まとめ】サポーターは“悪”ではない。だが、万能でもない。
・外反母趾サポーターは補助として役に立つ
・しかし“形”だけ整えても、外反母趾の本質は変わらない
・必要なのは 筋肉・神経・足指の再教育
・正しい使い方ができれば、サポーターは“助け”になる
外反母趾は足の「構造」と「機能」の両方を理解することが大切です。
あなたの足が本来持つ力を取り戻せるよう、この記事がきっかけになれば幸いです。
では、サポーターの代わりに「何を使えばいいのか?」
ここまで読んで、
「サポーターは万能ではないことは分かった」
「でも、何もしないのは不安」
そう感じた方も多いと思います。
ここで重要なのは、
“固定しないこと”と“何もしないこと”は全く違う
という点です。
外反母趾に本当に必要なのは、
- 足指が動ける余地があること
- 筋肉と神経の働きを邪魔しないこと
- 体操の時間だけでなく、日常の大半で使われ続けること
つまり
「無意識の時間をどう使うか」
です。
サポーターは“意識して着ける時間”の道具ですが、
外反母趾の影響を受けるのは、
仕事中・家事中・外出中といった無意識の時間です。
この視点が抜けると、
どれだけ理論が正しくても、現実は変わりません。


.017-1-scaled.jpeg)
.018-scaled.jpeg)
.016-scaled.jpeg)
.015-scaled.jpeg)
.014-scaled.jpeg)
.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)
.009-scaled.jpeg)
.008-scaled.jpeg)
.007-scaled.jpeg)
.006-scaled.jpeg)
.021-scaled.jpeg)
.022-scaled.jpeg)
.023-scaled.jpeg)
.024-scaled.jpeg)
.025-scaled.jpeg)
.026-scaled.jpeg)
.027-scaled.jpeg)
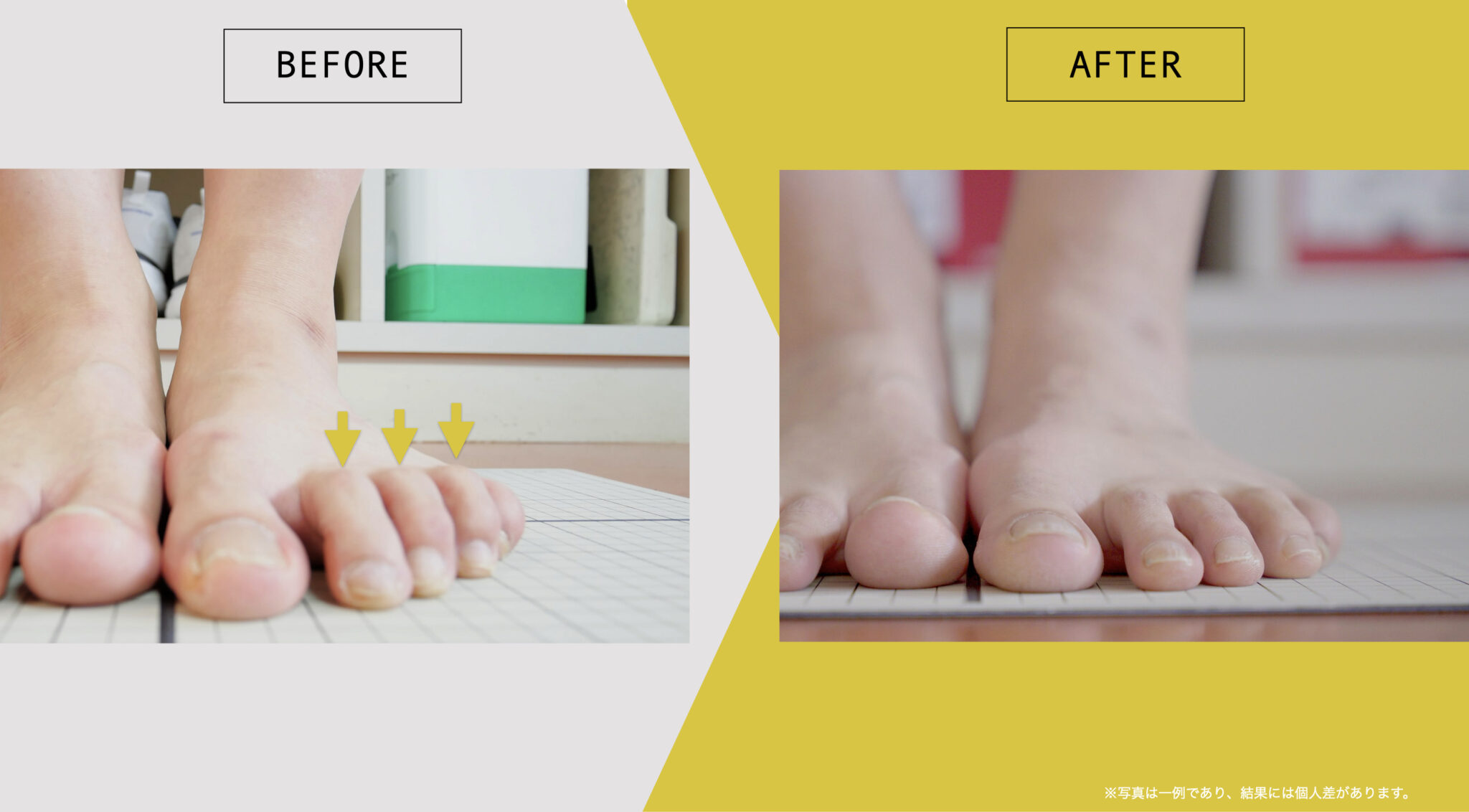



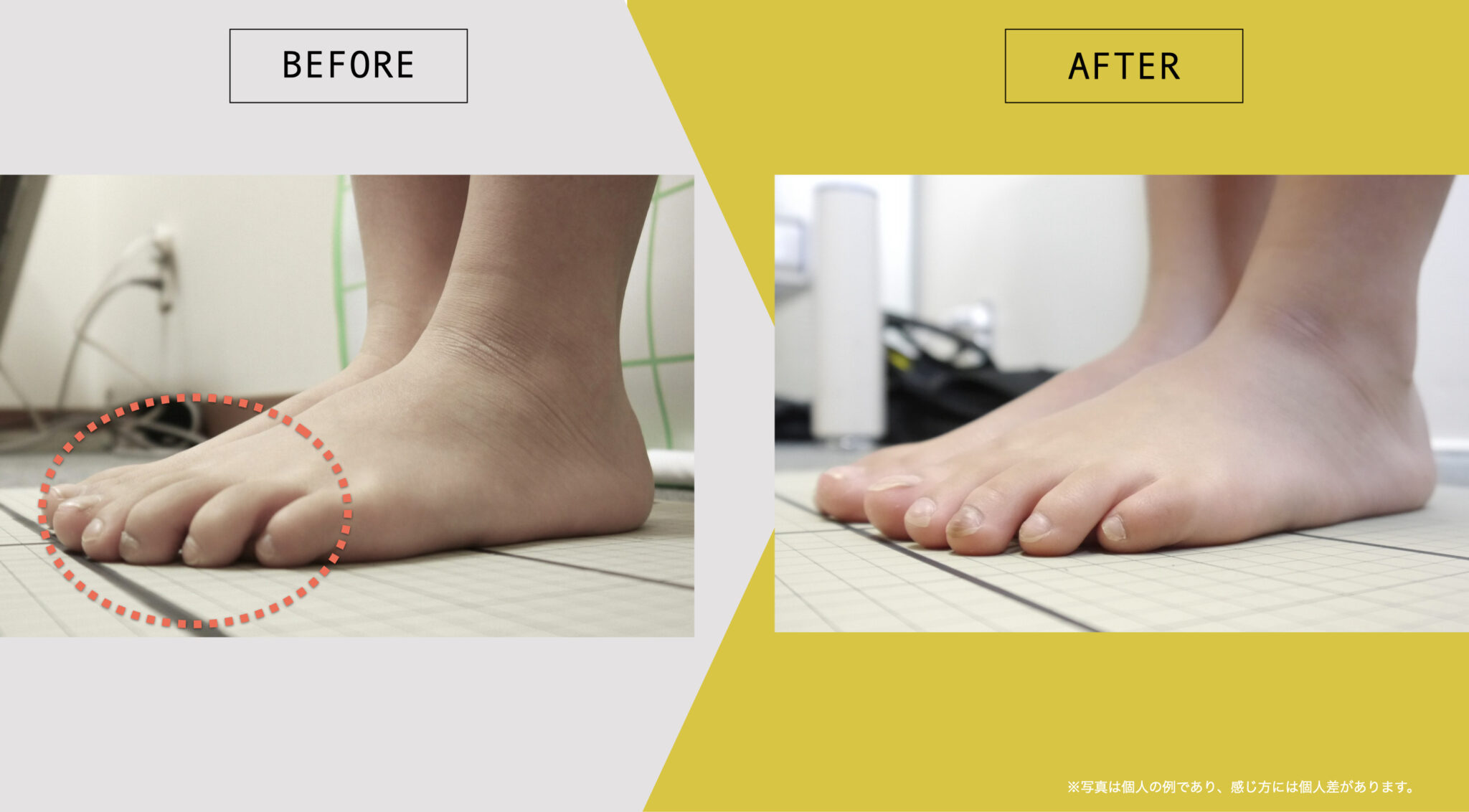


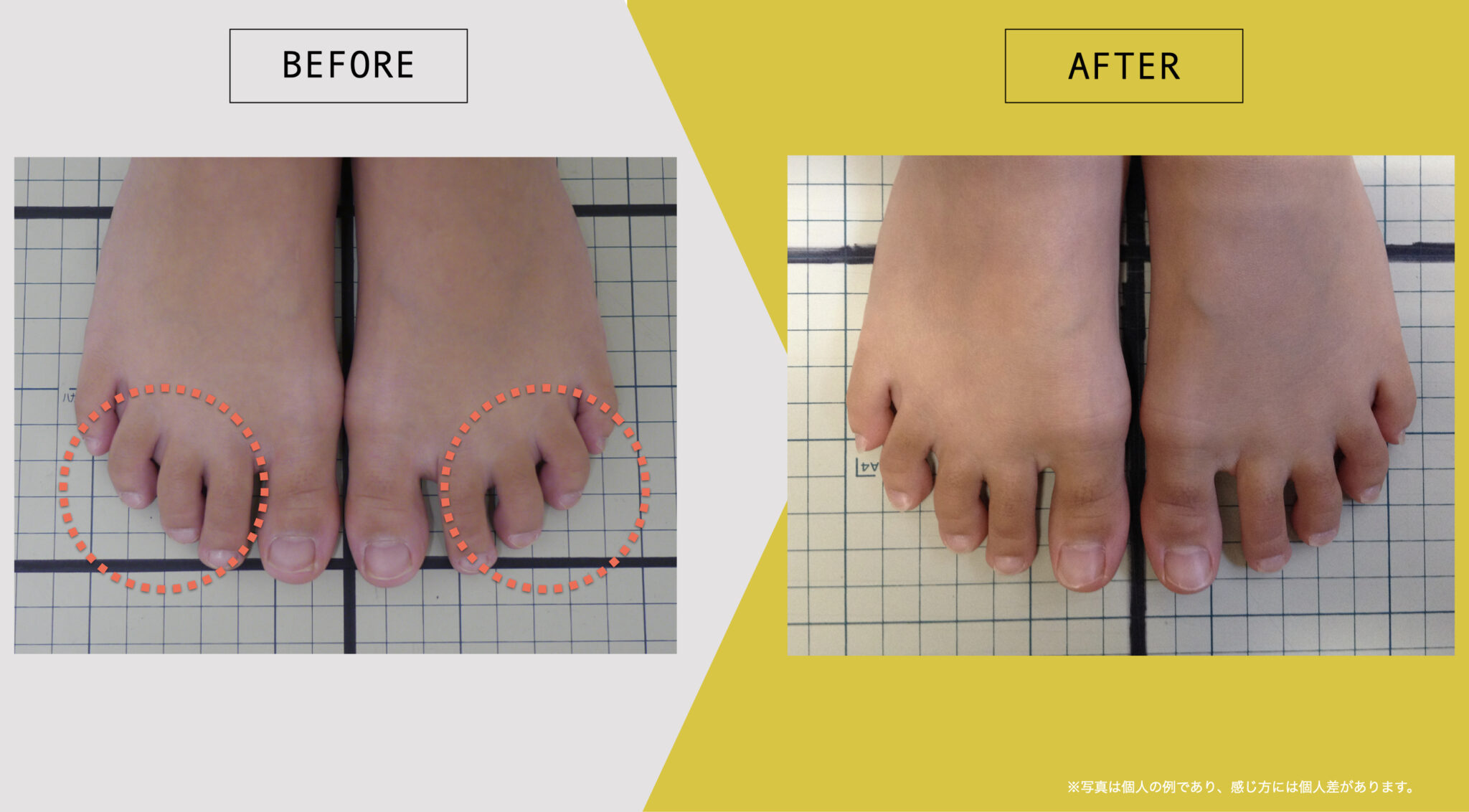


.083-scaled.jpeg)
.084-1024x566.jpeg)
.085-1024x566.jpeg)
.095-1024x566.jpeg)
.087-scaled.jpeg)
.088-scaled.jpeg)
.090-scaled.jpeg)
.092-1024x566.jpeg)
.093-1024x566.jpeg)
.096-1024x566.jpeg)
.097-1024x566.jpeg)
.098-1024x566.jpeg)
.094-1024x566.jpeg)
.100-1024x566.jpeg)
.091-scaled.jpeg)