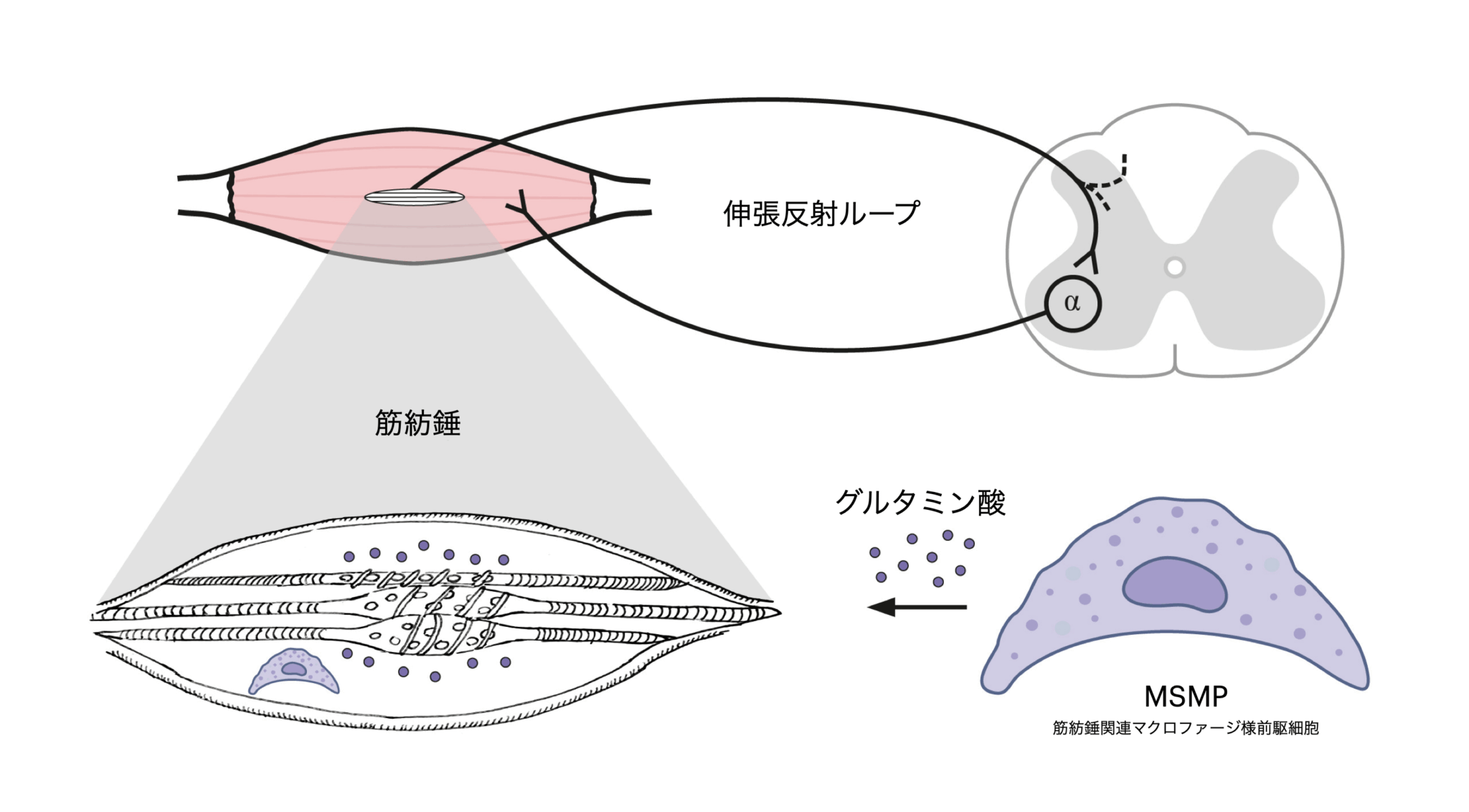【医療監修】体は“正しい順番”でしか変わらない?|足指から全身を再教育する「湯浅式4本柱」のメカニズム
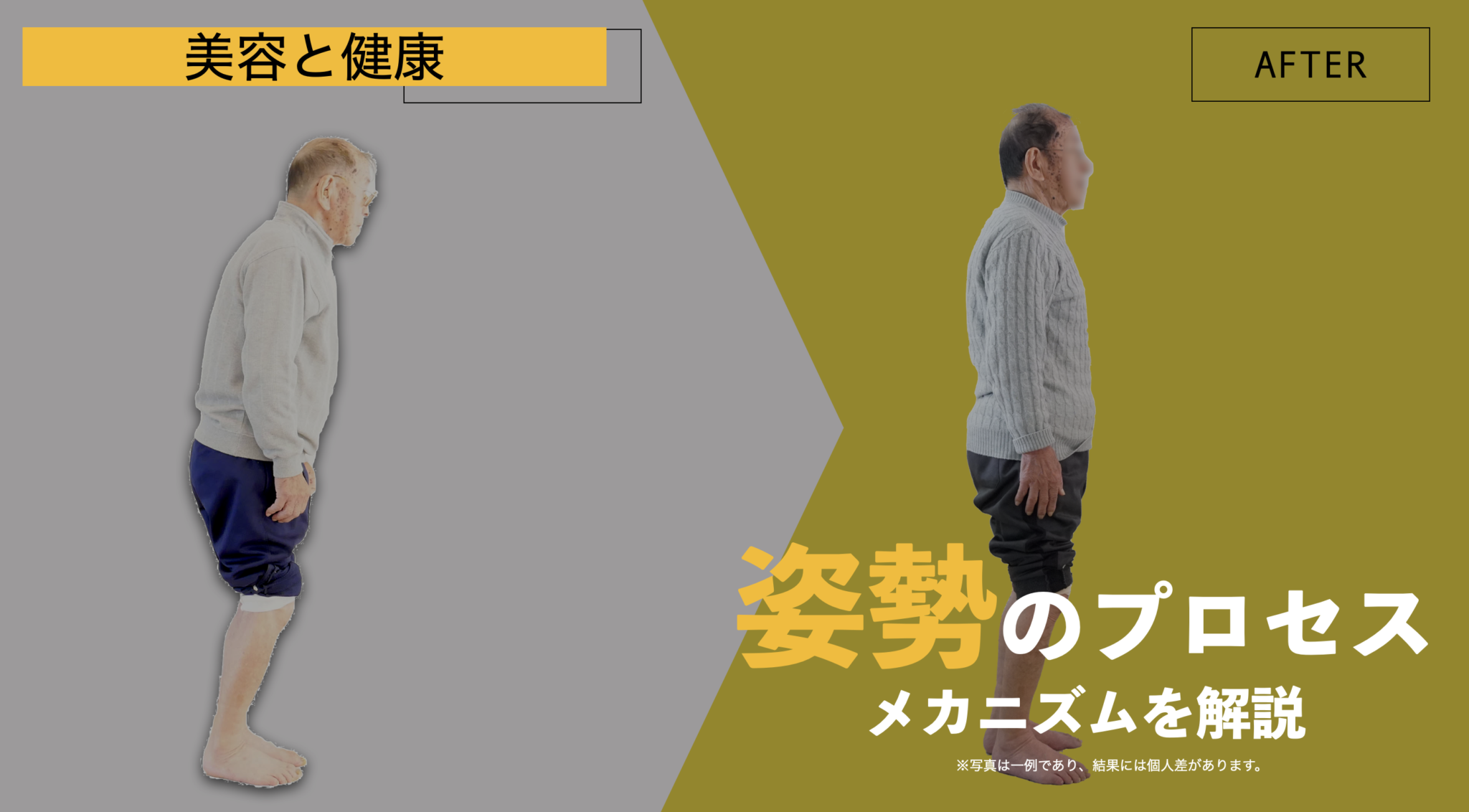
はじめに|なぜ多くの人は「正しくケアしているのに変わらない」のか
こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。
これまで10万人以上の足と姿勢を見てきた中で、多くの方が同じ悩みを抱えています。
- ストレッチしても姿勢が元に戻る
- 良い靴を買っても歩き方が変わらない
- 筋トレしても体幹が安定しない
これらは“方法が間違っている”のではなく、
ケアの順番が正しくない ことが根本にあります。
人間の身体は、
感覚 → 張力(トーン) → 構造 → 動作(運動学習)
という順序でしか再教育されません。
私はこの順序を、Hand-Standing理論として整理しています。
手で逆立ちをすると、指先が滑れば身体を支えられず、
力や意識以前に「構造として成立しない」状態になります。
人の姿勢や動作も同じで、
最下層の支持点(足指・足底)が機能していなければ、
どれだけ上でトレーニングやケアを行っても安定しません。
この考え方が、湯浅式「足指再教育の4本柱」の前提にあります。
湯浅式「足指再教育の4本柱」は、この生理学的プロセスに基づいた体系です。
【第1ステップ】ひろのば体操
—— 感覚と機能を“再び使える状態”へ起動する
現代人の足は
などによって、筋・腱・筋膜・神経の滑走が十分に働きにくい環境になることがあります。
滑走障害が起きると、
- 足指の反応がにぶく感じられる
- 本来の動きが出にくい
- 脳に送られる情報が不鮮明になる
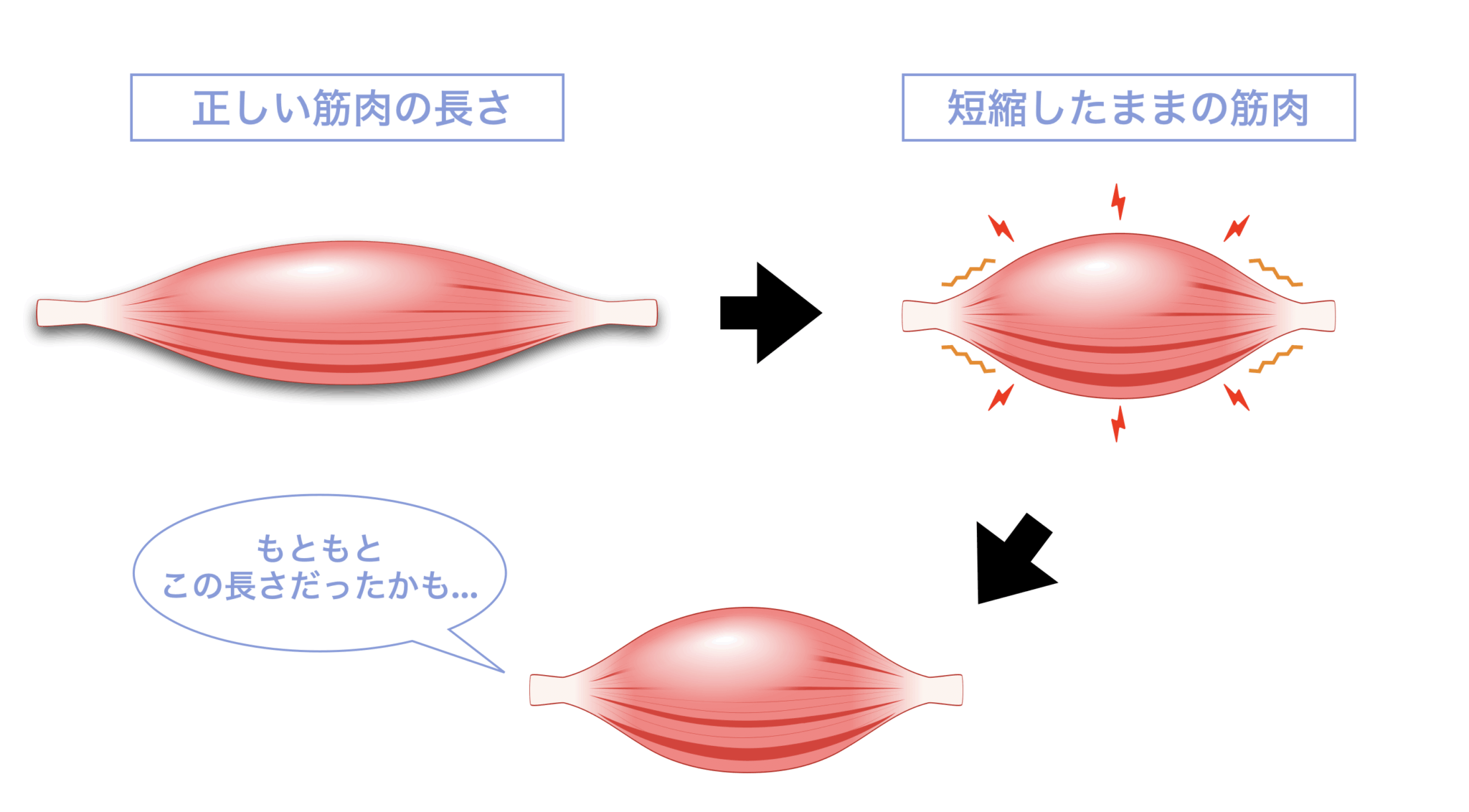
といった状態につながることがあります。
ひろのば体操は“神経回路の再起動を意識した準備”という位置づけです。
【第2ステップ】YOSHIRO SOCKS(Neural Matrix™)
—— 張力と形を“意識しやすい”環境をつくる生活用品

ひろのば体操で感覚が整ったあとは、
張力と足指の配置を意識しやすい環境づくりが大切です。
Neural Matrix™(ニューラル・マトリクス)は、日常生活において
- 足指の広がりを意識しやすい
- 滑走が過度に起きにくい
- 固有感覚の入力が安定しやすい
- 張力の偏りを避ける工夫がされた構造
を目指した生活用品です(医療機器ではありません)。
◎ 数値に基づく設計
- 摩擦係数:2.3N → 靴内での滑走を抑えるための設計要素
- 圧力:7.5〜8.5 gf/cm² → 足指まわりの張力過多を避ける工夫
- 伸張率:1.78倍 → 扇形の足指配置を意識しやすい構造
◎ 役割分担
- ひろのば体操:刺激入力を整える準備
- Neural Matrix™:張力と形を意識しやすい環境づくり
【第3ステップ】靴
—— 外的環境の安定化。「選ぶより“履き方”が重要」

靴は、足と地面の間に位置する“外的フレーム”です。
最重要ポイント
靴選びより「履き方が重要」
靴内で足が前滑りすると、
- 足指が屈曲方向へ引かれやすい
- 足底の張力バランスが崩れやすい
といった状態につながります。
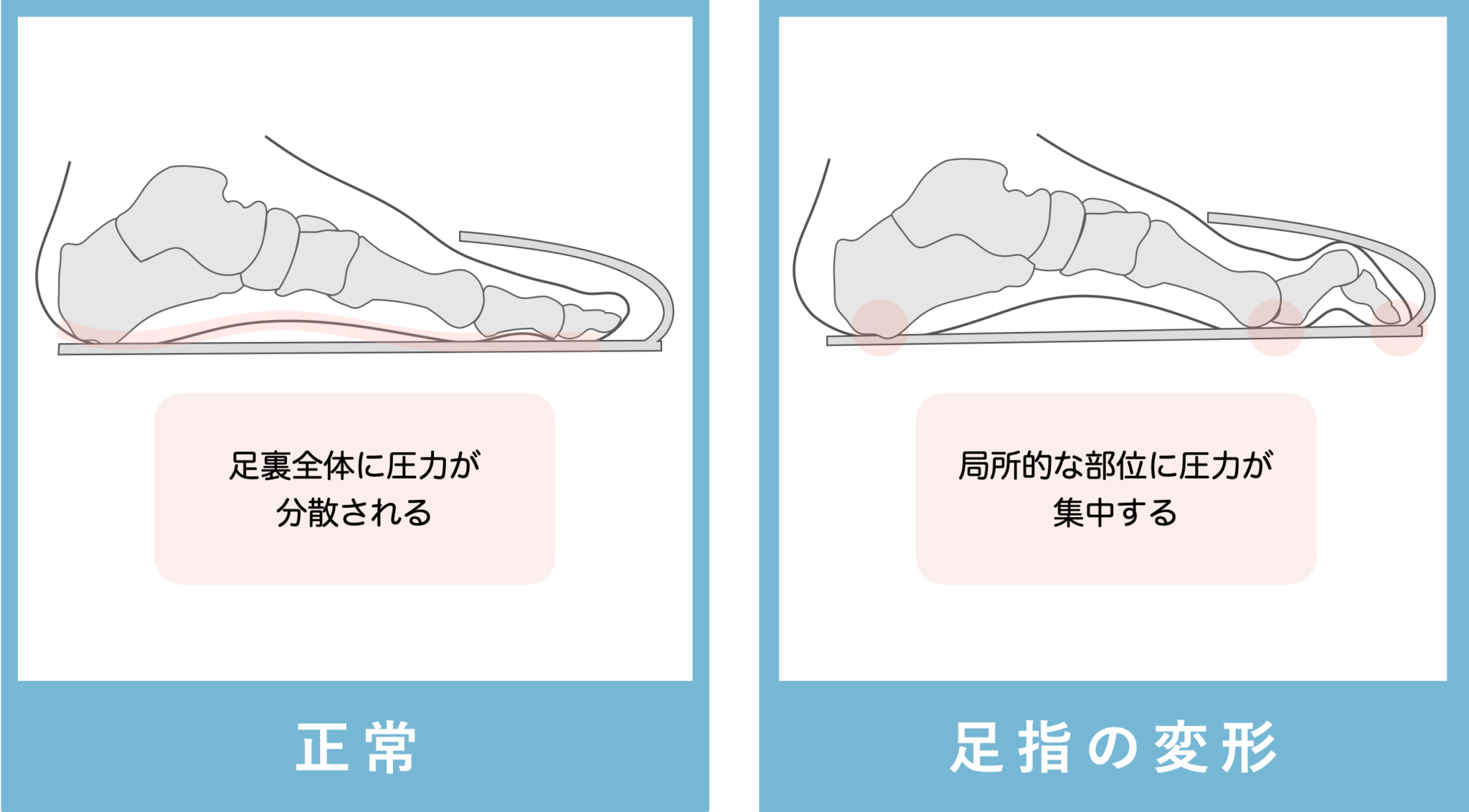
◎ 靴の条件
- 踵カウンターがしっかり
- 甲を紐で固定できる
- ソールがねじれにくい
- つま先に適度な余裕
本質は 踵を奥まで入れ、紐で固定すること です。

【第4ステップ】歩行
—— 無意識レベルで“自然な動き方を意識しやすい”段階
歩行は、身体の使い方を見直すうえで重要なステージです。
- 固有感覚
- 伸張反射
- 前庭
- 視覚
- 小脳統合
などが組み合わさり、
自然な動き方を意識しやすくなる一連の過程 と考えられます。
ひろのば体操 → Neural Matrix™ → 靴 → 歩行 の順番をそろえることで、
- 足底入力を意識しやすい
- 重心線の確認がしやすい
- 姿勢反射の理解が深まりやすい
といった“身体の学び直しに関わる要素”がそろいやすくなります。
まとめ|身体は「感覚 → 張力 → 構造 → 動作」の順番で見直すことが大切
湯浅式4本柱は、身体の使い方を再学習する際の順序を示したものです。
- 感覚の準備(ひろのば体操)
- 張力と形の環境づくり(YOSHIRO SOCKS / Neural Matrix™)
- 外的環境の整備(靴)
- 動作の再学習(歩行)
※これらは神経生理学・運動学・姿勢科学に基づいた考え方であり、治療や効果を示すものではありません。